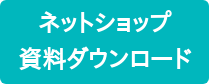カートまたはモールで自分のネットショップを開設したとき、商品を販売するまでにはショップ画面でいくつかの設定を行う必要があります。その設定の中でも一番頭を悩ませるものが、「商品コード」と「配送料」と言えます。そこで、今回は「商品コード」について、その重要性とつけ方を紹介します!
【関連記事】
商品コードを賢く設定する方法!【ネットショップの商品管理】
▼▼▼ネットショップをこれからはじめる方に向け、最初に押さえておくべきポイントをガイドブックにまとめました!是非ご活用ください。▼▼▼
目次
その商品コード安易に決めていません?!
ECサイトの登録はもちろん、商品の発注から配送、お客様の手元に届くまで必要になるのが商品コードです。
ほぼすべてのカート・モールで商品コードが必要となります。カートによっては「管理番号」・「ID]などと呼ぶこともありますが役割は同じです。
ショップ運営者以外にはあまりなじみはないでしょうが、これが商品情報を示す「鍵」となります。多くの場合この「鍵」は任意で設定できますが、「任意」と「適当」は異なるというのが現場のノウハウです。
商品コードを管理する必要性とは?
現在、国内に楽天やYahoo!などの代表的なモールからカートまで、大小含めるとなんと60以上ものネットショップを作れるサービスが存在しています。
商品を売るためには、まず商品を知ってもらう必要があります。商品の露出度を増やすために、複数のサイトへ登録されている人や、そろそろ違うモールやカートへ出店を検討している人も多いと思います。
そんな時、1つの商品に対して異なる商品コードを登録してはいませんか?1つの商品に対しモールによって複数のコードを登録することでいったい何が起きるのでしょうか?
一番起こりがちなトラブルは、管理が大変になり気付くとサイトへの登録を間違えてしまうトラブルです。
この登録間違い・管理間違いにより「商品はあるのにデータ上でモールAには在庫が登録されていなかった」「Bモールで売れけど、実際の在庫はないため出荷できていない」といった商品と在庫データに乖離が発生します。
また、商品の発注や配送代行サービスを利用する場合、取引先とやりとりするときは商品コードを使います。
その際、1つの商品に対して都度異なる商品コードを伝えてしまうと、発注した商品と違うものが納品されたり、配送代行会社で保管している在庫数がわからなくなったりとトラブルが発生しやすくなります。
トラブル回避のためにも、ここからは最適な商品コードを作るためのポイントをご紹介いたします!
1SKU=1商品コードが発注・販売管理で一番重要なポイント!
カラー違いやサイズ違いの商品を同じ商品コードで登録することは避けましょう。
物流の用語でSKU(Stock Keeping Unit)という言葉があります。受発注・在庫管理を行うときの、最小の管理単位をいいます。同じ商品でもパッケージ、入り数などの違いで区別し、アイテムよりも小さな単位に分類します。
例えばTシャツで、カラーが4色あり、サイズがS・M・L・LLの4種類ある場合、「16SKU」と数えます。
SKU毎に商品コードを作成することで別々に管理することが可能となり、カラーやサイズ別に売れ行きのデータ管理・発注数管理も簡単です!適切なタイミングで適切な商品数を発注・保管し、販売の施策を実施して売っていく…そんな理想的なネットショップの販売サイクルを作るための重要ポイントが1SKU=1商品コードです。
商品コードで使用できる記号や文字に注意
商品コードを作成するときは、記号はなるべく使用しないようにしましょう。
使いがちな記号の例として『!』や『@』『+』、『「』、『」』、『*』などがあります。こういった記号については一部のサイトなどで登録可能であっても、他のサイトで使えない可能性が高いです。
ただ、英数字のみの商品コードでは見づらい・違いがわかりづらいということもあります。そんな時にお勧めする記号は、『-』や『_』です。
たとえば、Mサイズの白色のTシャツの場合は、『Tshirt-M-white』とするとぱっと見でも分かりやすくなります。
・NG例 : STOCKCREW+001
・おすすめ例 : STOCKCREW-001
使用する文字は英数字のみ。漢字カタカナ平仮名はNG!
モールや管理システムの中にはひらがな等の文字が利用できるものもありますが、極少数です。基本的には英数字と一部の記号のみで作成しましょう。
商品コードの長さは30文字まで
商品コードの長さにも気を付けましょう。モールや在庫管理などのシステムによって登録できる商品コードの長さは異なります。商品の説明を事細かに入れることにより、長くなってしまう事もあります。新しいサイトに登録しようとしたときに、文字数がオーバーすることもあります。多くても30文字を目安として作成することをお勧めします。
NG例 : STOCKCREW-001-M-01-WHITECOLORLOGO (33文字)
おすすめ例 : SC-001-M-01-WHT-LOGO (20文字)
コードから商品が何かを判別できるようにする
商品コードはその名の通り『現物の商品』を示すコードです。商品コードから商品を特定できる様なコードを設定しましょう。実際の商品と商品コードに関連性が低いと、発注した際の誤納品の可能性が高まったり、在庫管理を行うときどの商品なのか分からなくなってしまう事もあります。
1番汎用性の高いコードは、『JANコード』です。JANコードはユニークなコード体系のため他社のものと重複することはありません。また商品に印字されていますので、簡単に商品を特定することができます。
まとめ
わかりやすく統一された商品コードを使用することで頻雑な管理や誤出荷のリスクを軽減することができます。
発送業務を配送代行サービスを委託するときにもスムーズな導入が可能となります。
商品を販売するとき最初に決める必要がある『商品コード』ですが、とりあえずよくわからないから何でもいいや!と思う作成してしまうと、途中で変更するのは様々なところで影響が出てしまいます。
今手元にある商品とこれから売りたい商品をともに考え、上記のポイントを参考にネットショップをしっかり運営するために商品コードを作成してみてはいかがでしょうか。
このほか、個人でネットショップ運営を軌道に乗せるために必要な情報を以下のリンクにまとめていますので、併せてご確認ください。
【2023年度版】ネットショップ運営完全ガイド〜個人で開業できる?おすすめのサービスは?ネットショップを始める方法を解説
STOCKCREWの配送代行サービスでは、サービス利用前にみなさんの商品コードを確認しています。まだ決めていないときは、商品コードの採番方法を提案もしていますので、お気軽にご相談ください。
 STOCKCREW(公式)
STOCKCREW(公式)