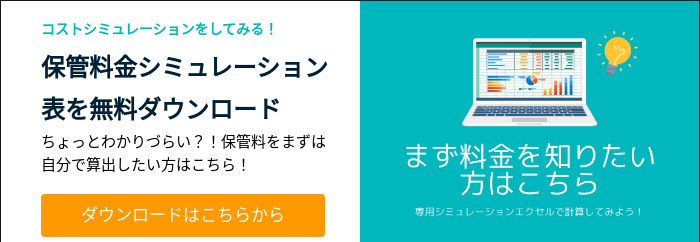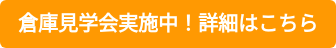ネットショップやEC運営において、重要な役割を果たす「発送代行」サービスについて解説します。発送代行を利用することで、発送業務を自動化することができ、本業に集中することができます。本記事では、発送代行を利用するメリットやデメリット、発注する際に注意すべきポイント、さらには適切な業者の選び方について詳しく説明していきます。
目次
発送代行とは?どんなサービス?
発送代行とは、ネットショップ運営者向けのEC物流を代行するサービスです。物流会社が入荷から出荷、輸送、配送、在庫管理などを代わりに行い、事業主に高品質かつ低価格なサービスを提供します。さらに、発送先を国内だけでなく海外にも広げることができるため、ビジネスの拡大や成長に役立ちます。このような発送代行サービスは、ビジネスの成長に欠かせないものと言えます。また、納品代行や物流代行、梱包代行などとも呼ばれることがあります。
自社でEC物流を行う場合、梱包資材の保管や配送会社との契約、商品の在庫管理など、すべての作業を自社のリソースで行わなければなりません。ネットショップを運営する際には、ECサイトの開設や商品の仕入れ、販売促進など、売上を増やすための様々な取り組みが必要です。そのため、発送作業に時間や労力を多く割いてしまうと、売上に直結する業務である仕入れや販促施策に支障をきたす可能性があります。
発送代行のおもなサービス内容
弊社STOCKCREWの倉庫内業務に関する動画の概要です。この動画をご覧いただくと、発送代行においてどのような作業が行われるか、より具体的なイメージを持っていただけるでしょう。
さらに、発送代行のおもなサービス内容をご紹介いたします。
- 商品の入荷業務
- 商品の在庫管理業務(保管)
- 商品の発送業務
- 商品の流通加工業務
- 物流業務の支援システムの提供
発送代行の業務は幅広くあり、ECの物流業務だけを提供することもあれば、フルフィルメントと呼ばれ、「ささげ業務(撮影・採寸・原稿)」までを提供することもあります。ここでは基本的な物流業務での発送代行について説明していきます。
発送代行の基本「物流業務」
発送代行サービスは、基本的な物流業務を担当しますが、いくつか特徴があります。上記の基本業務に加えて、発送代行サービスは複数の会社に対して提供されるため、共通の管理コードを発行する必要があります。また、入荷予定の作成や出荷納期のルールも非常に厳格です。
これらの特徴から、自社で発送業務を行っている方にとっては、発送代行サービスは柔軟性が制約されるように感じられるかもしれません。
「付帯作業」は発送代行運営会社によって差がつく!
「流通加工業務」という言葉は馴染みがないかもしれませんが、これは在庫管理の一環として、シール貼りや入荷検品などを行う業務を指します。また、商品の保護のために袋詰めや緩衝材を使った包装作業も含まれます。詳しい内容については、「物流加工とは?意外と知られていないその業務」で詳しく説明されています。
サービスを差別化する「システム」
「システム提供」は、発送代行サービスを利用する際に必要な入荷予定データや受注データなどをやり取りする仕組みを指します。近年では、このようなシステム提供を標準で実装している会社が増えています。
提供されるシステムのユーザーインターフェースや利用可能な機能は非常に重要で、ギフト対応や領収書対応、受注内容を特定のルールで変更するトリガー機能など、ネットショップでできることが拡大しています。
発送代行利用の増加理由は?
圧倒的な市場成長
発送代行の利用が増加している最大の理由は、ネットショップの開設が以前よりも簡単になり、その結果、事業者数が急激に増えたことにあります。ネットショップ運営のSAAS(ソフトウェアサービス)であるShopifyやBASEなどが、この市場を後押しし、個人事業者やスタートアップなどのD2C(直接消費者向け)事業者が急増しました。
当然のことながら、EC(電子商取引)市場が急速に成長している中で、EC事業者数も劇的に増加しました。このような事業者を支えるための物流サービスが不足したため、物流業界全体でその需要に対応してきたという状況が生まれました。
コスト削減としての発送代行
もう一つの理由は、物流費用の削減への期待です。スタートアップや個人事業主が発送業務を行う場合、安価な配送契約を締結することが難しいことがよくあります。しかし、発送代行業者は既に多くの配送実績を持っており、彼らを利用することで配送費用を削減できるという点が評価されています。各配送会社の比較や特徴、料金体系については、以下の記事で詳しくまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。
アウトソースでコア業務に集中
3つ目の理由は、販売業務に集中するために発送作業を自動化したいという要望です。受注データのAPI化や倉庫業務のロボット化、そして発送作業の自動化など、自社でこれらの業務を行うには大きな負担がかかるため、外部に委託することで自社のリソースを販売促進や新商品開発に集中させたいというのが自動化の主な目的です。
新規プロジェクトの立ち上げ
最後に、新規のブランドやプロジェクトを既存の物流とは別に管理したいという理由が挙げられます。なぜ別の管理方法を選びたいのかというと、既存の物流インフラで新しい取り組みを行うと、うまく機能している既存の部分にも影響が及ぶ可能性があるため、不安を抱えるからです。そのため、一旦は別の物流インフラを利用して新しい取り組みを始めたいという思いがあります。
これは従来の物流サービスが事業主ごとに最適な物流ソリューションを提供しカスタマイズしてきた経緯とは対照的な要望です。
この点は発送代行のメリットとデメリットにも関連しており、覚えておくと良いでしょう。
発送代行を利用する3つのメリット
発送代行の利用にあたって、基本的に以下の3つのメリットが挙げられます。
- 高品質なEC物流サービスをすぐに利用できる
- ネットショップの成長を維持・促進する出荷キャパシティを確保できる
- 発送業務のコストが利用した分だけのコストにできる(変動費化)
それぞれについて、詳しく解説していきます。
高品質なEC物流サービスをすぐに利用できる
発送代行を利用するメリットの最初のポイントは、品質の維持と向上を外部に委託できるという点です。
受注件数が少ない場合、自社で発送を行いながら品質を維持することは比較的容易です。しかし、取り扱う商品の数や出荷量が急激に増えると、品質を一貫して維持することは非常に困難になります。
一定の規模を超えると、アナログな手法では対応が難しくなり、機械化やロボット化が必要となってきます。しかし、物流設備に投資するには相当な規模が必要であり、投資対効果が見込めない場合もあります。既にデジタル化された管理を行っている発送代行業者を利用することで、大規模な投資なしに物流の品質を向上させることができるのです。
さらに、望ましくはありませんが、万が一誤出荷や在庫差異が発生した場合に、その損害の補償を外部に委託できるというメリットもあります。自社で発送を行った場合、品質の問題が生じた場合は自社で全ての負担を負わなければなりませんが、発送代行を利用することで一定の補償範囲内で負担を外部に分散させることができます。
ネットショップの成長を維持・促進する出荷キャパシティを確保
ネットショップは、インフルエンサーの起用やSEOの成功によって急激に受注件数が増加することは珍しくありません。こうした予期せぬ成功に対しても、ネットショップのメリット・強みは、しっかりと準備をして納期遅延を起こさずに確実に出荷できることです。ただし、自社発送では十分な準備ができない場合もあります。
また、安定した出荷と並んで、十分な在庫量の確保も重要です。在庫を十分に準備できていないと、マーケティング施策も無駄になってしまい、避けたい状況です。
一方で、在庫を多く持ちすぎると事業の収益に圧力をかけるため、健全な在庫管理が求められます。そこで、発送代行の利用を通じて、自社発送ではできないスペースの確保をタイムリーに行い、物流インフラが自社の成長を阻害する状況を避けることができます。ネットショップの在庫管理については、「もっと重要視すべき!ネットショップの在庫管理」という記事で詳しく説明しています。
ネットショップの成功には、準備と在庫管理の重要性が欠かせません。
発送業務のコストが利用した分だけのコストにできる(変動費化)
多くの発送代行業者が「初期費用・固定費0円」と宣伝しており、物流費を変動費として扱えるというのは大きなメリットです。
また、季節性の高い商品の保管は、物流インフラを構築する際の課題の一つです。一定期間だけ倉庫を確保することは可能ですが、毎年条件が合う倉庫を用意することは必ずしも簡単ではありません。そのような場合、利用した分だけ請求される発送代行サービスは魅力的な選択肢となります。
受注件数が少ない場合でも、コスト削減は重要な課題です。しかし、発送業務はネットショップ運営において必要不可欠な業務でもあります。その際に、人件費が固定費として発生してしまう自社発送よりも、発送代行を利用して受注件数に応じて費用が発生する仕組みは頼もしいと言えます。
発送代行のデメリット3つ
発送代行を利用するメリットに続いては、デメリットも紹介します。こちらもおよそ3つのデメリットが挙げられます。
- 自社に合わせた柔軟な対応が難しくなる
- 物流ノウハウの蓄積が進まない
- 個人情報流出のリスク
自社だけに合わせた柔軟な対応が難しくなる
ネットショップ運営では、顧客との接点は配送時の梱包物や商品、付属のチラシなどに限られます。そのため、限られたリソースを活用して顧客のロイヤリティを確保するために、これらをブランディングしたいというニーズがあります。しかし、発送代行サービスの選択次第では、満足のいくブランディングができない場合もあります。
発送代行サービスは、複数のネットショップの発送を代行することでコストメリットを得ています。そのため、商品がどのネットショップのものかを特定できる必要があります。商品が半製品状態であったり、複雑な流通加工を経て製品として管理できない場合は、扱いが難しいと判断されるでしょう。
商品の状態だけでなく、発送代行サービスを利用する上で特定の手順に従う必要もあります。特に、商品コードやJANコードの記載、仕入れ元からのデータ入力のタイミングなど、商品管理に必要な情報の遵守が求められます。これらの運用ルールに従わない場合、発送代行サービスは使いづらくなります。
物流ノウハウの蓄積が進まない。
自社物流を行う場合、倉庫賃料や作業員の人件費など、大きな初期投資が必要になります。しかし、発送代行を利用すると、これらの投資を外部化するメリットがあります。一方で、最初から発送代行を利用し続けると、安定した物流を確保するためのノウハウを自社で獲得できない可能性もあります。
また、システム面でも同様の課題があります。発送代行サービスの具体的なオペレーション内容を正確に理解することは困難です。発送代行サービス側は複数のネットショップの発送を担当しており、特定の会社にすべての情報を開示することはできません。そのため、「物流システムのブラックボックス化」という状況が生じる可能性があります。
このような物流実績の不足は、配送会社との契約においても問題が生じる可能性があります。配送会社は過去の実績を非常に重視するため、発送代行サービスの契約金額を下回る条件での契約は稀であると考えるべきです。
そのため、他の条件が整っていても、配送会社との契約が円滑に進まず、自社発送に切り替えることを断念する場合もあります。発送代行サービスに最初から業務委託すると、こうしたノウハウを社内に蓄積できない懸念があります。
個人情報の流出のリスクがある。
ネットショップで利用される受注データの一覧は膨大な個人情報の塊であり、万が一流出した場合は事業運営を続ける上で大きなリスクになります。
そのため、発送代行側がどのような個人情報管理を行っているかをあらかじめ確認しておく必要があります。
発送代行サービスの3つの料金体系
ネットショップの運営で発送代行の利用は増加傾向にあります。発送業務の代行は品質も当然重要ではありますが、商品の仕入れ代と並んで大きなコストになる物流費を適正に管理したいという思いは強いかと思います。
今回はそんな発送代行の料金についてどのような料金体系があるのかを解説し、どのような費用項目で請求されるのかを解説していきます。
発送代行サービス会社の料金体系
まずご紹介するのは今、もっとも増えているネットショップ向けにサービス提供をしている会社の料金体系です。
発送代行サービスの料金は下のような費用項目で請求されるのが一般的で、また、初期費用・固定費がかからないサービスが多いというのも特徴です。参考に当社の料金表を載せておりますので、イメージを掴んでもらえればと思います。
- 1件・1点の発送費用
- 追加ピッキング費用
- 保管費用
- 発送代行サービス会社を利用する際の注意点

1件・1点の発送費用
1件1 点の発送費用と記載されている場合、以下の内容が含まれることが多いです。
- 1点分のピッキング費用
- 1件分の梱包作業費用
- 1件分の全国一律の配送費用
- 梱包資材・緩衝材
- 納品書同梱費用
- システム利用料
| サイズ | DMサイズ | コンパクト | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
相場料金 |
300~350円 |
550~600円 |
600~700円 |
700~800円 |
800~900円 |
追加ピッキング費用
料金体系に記載されている費用としての2つ目は1件の受注で複数点購入された場合の2点目以降のピッキング費用です。
保管費用
次に保管費用ですが、大きく分けて二つの請求の仕方があります。
- 体積に基づく保管費用
- 点数に基づく保管費用
保管費用は、サイズごとに1点1日の料金が提示されます。しかし、物流業界でよく使われる「三辺サイズの合計」計算方法には注意が必要です。
なぜなら、「三辺サイズの合計」は商品の大きさを正確に反映できないからです。例えば、同じ60サイズと言っても、各辺が20cmの立方体と30cm×25cm×3cmの平たいアパレル商品では、容積は8000㎤と2150㎤という4倍近い差があります。そのため、三辺サイズの合計だけで保管料金を請求すると、立方体に近い商品はお得になりますが、平たい商品では損をすることになります。
つまり、三辺サイズの合計だけで商品の大きさを評価すると、平たい商品の実際の容積を適切に反映できず、公平な料金設定が難しくなるのです。
| サイズ | DMサイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
|---|---|---|---|---|
相場料金 |
0.3~0.5円 |
0.7~1円 |
2~3円 |
4~5円 |
発送代行サービス会社を利用する際の注意点
発送代行サービス会社の料金表の特徴は以下の通りです。
- 初期費用・固定費がかからない始めやすいサービスになっている。
- 発送費用に関連費用が含まれておりわかりやすい料金になっている。
- 利用した分だけの請求になっており、波動の変動を加味している。
注意すべき点として、発送代行の料金体系はわかりやすい一方で、平均的な商品や販売手法ではない場合に割高になる傾向があります。
例えば、アパレル商材の場合、保管料が高くなることがあります。また、発送料も全国一律というメリットがありますが、商圏が都市圏に偏っている場合は割高になる可能性があります。
つまり、発送代行サービスは一般的な商品や販売方法に適しており、料金体系もわかりやすいですが、特殊な商品や販売手法の場合は注意が必要です。アパレル商品のように保管料が高くなったり、商圏が限定的な場合は割高になることがあるのです。
倉庫・物流会社の料金体系
倉庫・物流会社の料金体系は、発送代行サービスと比較すると「単位別に細かい」という特徴があります。ただし、実際に行われる業務は発送代行サービスと同じであり、料金体系の違いは見せ方によるものです。
倉庫・物流会社の見積書では、具体的な業務単位ごとに料金が詳細に示されます。これにより、保管料、梱包作業、配送などの各項目ごとに料金を把握することができます。例えば、保管料、商品の仕分け作業、パレットへの積み替えなど、それぞれの業務に対して個別の料金が設定されます。
このような単位別の料金体系は、業務ごとに費用を見積もる際に細かい部分まで考慮できる利点があります。しかし、一方で見積もりの作成や料金の把握が複雑になる可能性もあります。
要するに、倉庫・物流会社の料金体系は発送代行サービスと同じ業務を行いますが、見積書の作成や料金の詳細表示方法が異なることが特徴です。
- 入荷費用
- ピッキング費用
- 梱包費用
- 配送費用
- 保管費用
- システム費用
- 倉庫・物流会社を起用する際の注意点
見積書イメージ
| 大項目 | 小項目 | 単位 | 参考単価 |
|---|---|---|---|
入荷関連 |
入荷料金 |
点/ケース |
10円/100円 |
入荷関連 |
入荷検品料金 |
点 |
20~30円 |
出荷関連 |
ピッキング費用 |
点 |
20~30円 |
出荷関連 |
梱包費用 |
件 |
50〜150円 |
出荷関連 |
梱包資材費 |
件 |
20~100円 |
出荷関連 |
納品書同梱 |
件 |
5~20円 |
配送関連 |
大手3社 |
件 |
450~550円 |
保管関連 |
坪 |
坪/月 |
5,000~7,000円 |
保管関連 |
パレット |
パレット/月 |
2,000~3,000円 |
システム関連 |
WMS利用料 |
月額 |
10,000~30,000円 |
入荷費用
入荷料金はケースか点数に対して課金されます。これは実際の商材によって変わってくるのですが、化粧品やサプリなどのメーカーの納品精度が高い場合には外装検品と呼べれる箱を開けない形での検品を行い、その場合はケースで課金し、アパレルや雑貨などの生産工程で生産量にばらつきが生まれやすい商材については点数で行われる傾向があります。
ピッキング費用
ピッキング費用は見積書では1項目にしておりますが、サイズ別や商材別に設定されることもあります。特に取扱SKU数が多い場合にピッキング費用は高くなっていく傾向があるので要注意です。
梱包費用
梱包費用はピッキング費用に含まれる場合もあります。通販の出荷では梱包作業の工程が多くなることが多く別項目として請求されるケースが多いように感じます。作業内容としてはピッキングで集品した商品を発送用の資材に梱包し、送り状を貼付する作業に当たります。
配送費用
配送費用は全国一律ではなく、サイズ別・地帯別に設定されるケースが多いです。特に店舗や拠点への出荷が多く任意の地域に発送することを前提としている場合は地帯別になります。
発送地域が予め把握できるような場合は全国一律よりも相対的に安価になります。
保管費用
保管費用は使用面積に基づいて請求されます。保管の単位は以下の3つになります。
- 坪単位(3.3㎡)
- パレット単位(1.21㎡)
- 棚単位
請求の仕方は日割り計算や月額、三期制など様々です。こちらについては「4つのポイントで保管料を徹底比較!~保管料の単位と計算~」にて詳細に説明していますので、ご確認ください。
倉庫・物流会社を起用する際の注意点
倉庫・物流会社の料金体系の特徴をまとめると以下の通りになります。
- 作業単位別の細かい単価設定
- 地帯別・サイズ別の配送料金
- 固定/変動など商材に合わせた保管料金
この料金体系のメリットは実際の業務と単価の関係を把握しやすく料金の透明性が高いことです。一方で内容が細かいために物流について詳しくないと思い違いや認識違いが起こりやすく思わぬ物流費が発生してしまう可能性があります。
特に配送サイズや保管形態については倉庫現場での運用方法に依存する部分が多く、誤解が生じやすい項目なので一層注意が必要です。
FBA・RSL納品代行会社の料金体系
最後に納品代行会社の料金体系についても説明しておきます。納品代行会社は今まで説明した発送代行や倉庫・物流会社とは異なり、直接消費者に届ける通販の物流ではなく、FBAやRSLに納品代行することをメインにサービス提供している会社になります。そのため、荷動きが点数単位ではなくケース単位での請求単位になることが一般的です。
- 入荷費用
- 出荷費用
- 保管費用
- 流通加工費用
- FBA・RSL納品代行会社を利用する際の注意点
見積書イメージ
| 大項目 | 小項目 | 単位 | 参考単価 |
|---|---|---|---|
入荷関連 |
入荷料金 |
点/ケース |
10円/100円 |
入荷関連 |
入荷検品 |
点 |
10円 |
出荷関連 |
ピッキング費用 |
点 |
10~20円 |
出荷関連 |
出荷費用 |
件 |
100~200円 |
配送関連 |
配送料 |
件 |
拠点別 |
保管関連 |
坪 |
坪/月 |
5,000~7,000円 |
保管関連 |
パレット |
パレット/月 |
2,000~3,000円 |
保管関連 |
棚 |
月 |
2,000~3,000円 |
入荷費用
納品代行の入荷費用は点数単位・ケース単位で請求されます。海外でFBAラベルが貼付されていて流通加工が必要のない場合などは特にケース単位での請求になります。倉庫内で流通加工が必要であり、セット組やシール貼付が必要になる場合には点数での請求対象になります。
出荷費用
出荷費用は点数単位・ケース単位で行われますが、点数単位で行われた場合でもネットショップでの発送費用と比較すると安価な料金設定がされている場合が多いです。これは配送先がランダムに複数なネットショップでの発送業務と比較して納品代行の発送業務では特定の拠点への出荷を前提としているために業務工数が少ないことが関係しています。
【関連記事】
発送代行での利用率が高い「ヤマト運輸」の配送サービスを解説!
発送代行での利用率が高い「佐川急便」の配送サービスを解説!
発送代行での利用率が高い「日本郵便」の配送サービスを解説!
保管費用
保管費用は坪・パレット・棚で請求されます。基本的には倉庫・物流会社の保管と同じ内容になりますが、納品代行では納品スケジュールが決まっている場合が多く、保管を目的せずあくまでも流通加工を目的としていることから保管料が相対的に安価に設定される傾向があります。
流通加工費用
納品代行を利用する際の目的は発送業務よりも流通加工業務にある場合が多いです。FBAやRSLの納品には厳格な納品ルールがあり、海外で対応できないような流通加工を国内倉庫で行うといった場合に利用されます。
FBA納品ではシール貼付や袋入れが納品時に必須の業務になることが多く、そうした際に利用されます。
FBA・RSL納品代行会社を利用する際の注意点
納品代行会社の料金体系の特徴は以下の通りです。
- 全体的にシンプルな料金体系になっている。
- ネットショップの発送業務は行わず拠点への納品をメインとしている。
- 保管料や出荷料が全体的に安価に設定されている。
ネットショップ運営をしていて同時に納品代行も利用したいというニーズは多いと思います。そうした際に実はネットショップの発送代行を行う会社でFBA納品を行うように専業の納品代行を利用した方がトータルでコストが安くなるということもあります。一方で拠点間の輸送に追加のコストが発生しますので在庫コントロールを正確に行えないと無駄なコストが発生する原因にもなります。
発送代行の業者を選ぶ際のポイント
発送代行業者を選ぶポイントを紹介する前に、どのタイミングで発送代行を依頼すべきなのでしょうか? それは、自分で発送業務を行うのが手間になってきた、という時期がベターです。綿密に費用面などを考えて……などは行わず、まずは軽い気持ちで検討、見積もりの依頼といった流れで問題ありません。ここからはどのようなポイントで発送代行を選べばよいのかを解説します。
サービスの提供価格
発送代行の料金は比較検討がしやすくなっておりますので、しっかりと料金体系を踏まえて検討してください。また、大切なのは全体の見積もりではなく、特に自分が利用する価格帯の料金ですので、自社の商材に適用される料金をしっかりと吟味することが大切です。
サポート体制
商談時には見えない部分なのですが、商品を預けるサービスですので、実際に運用が始まった後の運用サポートが重要になります。例えば、入荷遅延や不備があった際にどの程度のスピード感で対応してもらえるのか? 商品に不備があった際の在庫確認はどの程度の時間軸で対応してもらえるのか? こういった料金に見えない部分がとなりますので、しっかりと見定める必要があります。
API連携対象
発送代行を依頼する大きな要因として、運用の手間の削減があります。その観点で言うとAPI連携の可否は非常に重要であり、API連携ができないとCSVでの日々の運用が残ってしまいます。発送代行のシステムが自社のカートシステムとしっかり連携できるか否かを確認する必要があります。カートとのAPIを利用しての発送代行については以下の記事でもまとめておりますので、参考にしてください。
稼働倉庫の視察
発送代行サービスには倉庫運用を含めて行っている事業者と再委託で行っている事業者があります。再委託の場合、品質管理等は委託先の倉庫が実際には行うことになり、商談時の担当がどれだけ対応がよかったとしても運用後の品質は低下してしまいます。そういったリスクを避けるためにも実際に荷物を預ける倉庫の視察を事前に行うことをおすすめします。
取扱実績
最後に自社の商材の取扱実績を確認してください。商材によっては特殊な管理が求められたり、FBA等の納品条件等が特殊であったりし、そういったことのノウハウの有無はストレスなく委託する上で非常に重要になります。特に化粧品等のリピート通販は通常の通販とは異なり同梱物やキャンペーンなどの取り組みが必須になるため、このあたりのノウハウの有無は必ず確認しておきたいところです。
発送代行を提供するサービス・業者7選
最後に発送代行を提供する代表的な7社を紹介します。
STOCKCREW
EC物流にはさまざまな企業がありますが、大手になるほど料金システムが複雑になりがちです。大手に比べSTOCKCREWでは分かりやすい料金システムを実現しているのが特徴です。
STOCKCREWでは、初期費用も固定費用も0円で掛かりません。発送代行を使いたいがコストに不安を覚えているかたでも安心して使えます。これは大手にはないサービスでもあり、小さなショップでもその利便性を十分に享受いただけます。
小さなショップのみならず、個人の方のご利用も大歓迎です。実際にSTOCKCREWでは多数の個人のお客様にもご利用いただいています。この不安に関しては「個人でも発送代行サービスを利用しても大丈夫?」もぜひご確認ください。
API連携、ロボットによる自動化、そしてさまざまなデータを管理できるシステムを実現できるセンターを2拠点用意し、徹底的な効率化を図っています。こうした企業努力により、他社と比較して非常に安い価格設定になっているのが大きな特徴です。それ以外にも、大手とは違ったきめ細やかなサポート体制を利用できる環境が整っているのも自慢のひとつ。STOCKCREWのEC物流をより知りたい方は是非「STOCKCREWとは?我々の内側全部見せます!倉庫編」もご覧ください!
はぴロジ
Shopifyとの連携が強みのはぴロジは、「ASIMS」というShopifyとのデータ連携が可能なクラウドシステムを導入しています。常時データ取込みを行っており、受注時には自動で出荷指示を倉庫へ送るため、効率的な作業を実現。また、全1200社以上が利用する「AiR Logi クラウドWMS」との連携も特徴として挙げられます。
オープンロジ
オープンロジは物流アウトソーシングのプラットフォームで、STORESとの連携が容易なのが特徴。管理画面からの発送依頼が可能で、PCやスマホからもアクセスできます。固定費はかからず、従量課金制で商品1点からの発送ができます。ECサイトを新規に立ち上げたり、少量の依頼をしたい場合に最適なサービスとなっています。なお、海外配送は非対応となっています。
ロジー.com
ロジー.comは、自動梱包機とクラウド型管理システムを導入し、「保管費0円」という魅力的な料金設定を実現しています。出荷指示は1日わずか3分で完了する手軽さで、契約継続率は99.8%を誇っているとのこと。各モールやネット通販の受注データをロジー.comのクラウドに簡単にアップロードでき、特殊商材の取り扱い許可として、高度管理医療機器の免許を保有しており、医療機器の出荷も可能な点も注目です。
株式会社スクロール360
浜松市に拠点を持つ株式会社スクロール360は、発送代行業者としてのみならず、EC運営全般のサポートを得意としています。スクロール360の最大の特徴は、物流からマーケティングまでの一連の業務をワンストップで提供すること。これにより、複数の企業とのやり取りや調整の手間を大幅に減少させることができます。
ウルロジ
ウルロジでは、オンライン上での手続きだけで商品の入庫から出荷までの一連の業務を迅速に対応します。13時までの出荷指示は、その日のうちに出荷できるのが強み。そして、物流の専門家がサポートするため、どんな物流の課題も気軽に相談できるのも注目ポイントです。
日新ECパートナーズ
株式会社日新ECパートナーズは、商品の入荷から保管、そして発送までの一連の業務をワンストップでの提供が強みです。大型商品の取り扱いにも長けており、商品の点数が増えたり、売上が急増した場合でも迅速に対応しています。さらに、配送や出荷のミスを最小限に抑えるため、物流の専門家がバーコードを活用して商品をデジタルで管理しています。
業務効率化&売上向上…発送代行を利用しませんか?
ここまで発送代行の内容、メリット・デメリット、料金体系とその相場を説明してきました。ここに記載されていることを念頭に発送代行の選定を行えば、致命的なミスは避けられるでしょう。
発送代行を提供する側にも得意なサイズや得意な商材というのは必ずあります。あるサイズ帯の価格は安価だが、それ以外が相対的に高い、ということもあります。
ですから、起用する際に全体を見るのではなく、しっかりと自社の商材にフィットした発送代行を起用することが重要です。
そして、発送代行側が複数社の発送代行を請け負うことでコストメリット、高品質を提供していることを理解し、起用後に自社向けの特別な対応が難しい可能性があることを把握しておきましょう。そうすることで委託すべき範囲とそうでない範囲が明確になり、賢く発送代行を起用できます。
また、自社の事業戦略次第では時として発送代行から自社発送に切り替えた方が良いという場合もあります。そうした時に事業戦略に沿った対応ができるように物流ノウハウの蓄積やインフラへの投資を進める必要があります。短期的だけではなく、中長期的にやるべきことを考えた上で発送代行と付き合うことが重要になります。
発送代行の説明についてはここまでになりますが、追加の疑問や具体的な見積もり、運用を知りたいという方は、ぜひ下のボタンからお問い合わせください!
 STOCKCREW(公式)
STOCKCREW(公式)